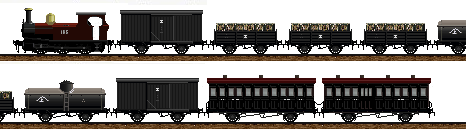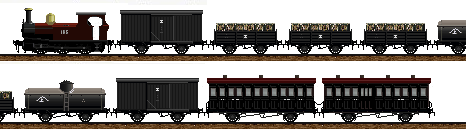ある機関車の生涯(或いは強運のボイラー)
明治31年5月。山陽鉄道広島駅構内の外れに数両の蒸気機関車が停められていた。内1両には数人の人夫が群がって解体作業をしている。解体されている機関車は日本鉄道Db3/3。通番186号である。その年の3月に火を落とし、大勢の職員に見送られながら棲家の小山機関庫を出発し、遥々旅をしてきたのである。
他の機関車には筵が掛けられている。やがてはこの機関車と同じ運命を辿るのであろう。
折からの霖雨の中、解体作業は徐々に進んで行く。リベットの一個一個が慎重に削られ、運転台が外される。ボイラーバンドが丁寧に除去される。外された部品は一つ一つ梱包されて隣の貨車に載せられて行く。
数日後、眩いばかりの五月晴れの下、数台の貨車に分乗した「元186号機」は、或いは二度と戻れない事になるかもしれない旅に出発して行ったのだ。行く先は宇品、そして艀に乗り換えて呉を目指す事になる。
日清戦争後の所謂三国干渉は、それまで日本が漠然と感じていたロシアの南下政策が突如として表舞台に噴出した事件であった。それ以後日本は軍事力、殊に海軍力の増強に狂奔する事になる。
間接的には海外市場で通用する日本の物産を片端から売りに出して外貨を稼ぎ、軍艦の購入に宛てる。大鑑、殊に戦艦は発注から受領まで数年掛かるのが常識で、その意味からも一刻の猶予がならない状況であった。
もっと直接的に、自力で艦船を整える事も考慮された。しかし明治30年代初頭の日本の技術力、資本力では戦艦、装甲巡洋艦等の大型艦艇を建造する事は土台無理な話であった。しかしながら小型の補助艦艇であれば、多少とも国産で補う事が出来る。
その小型艇の切り札が水雷艇であった。
機械水雷、所謂「魚雷」の発明はすぐさま水雷艇の発達に帰結した。小型の汽艇に発射装置を備え付け、敵の大型艦に忍び寄り、至近距離から大威力の魚雷を放って致命傷を負わせる艦種である。日本海軍は早くも明治15年にイギリス・ソーニクロフト社に発注をしており、日清戦争中、威海衛泊地における水雷艇の集中使用とそこで上げた実績は、各国海軍関係者の注目を集めた。
水雷艇自体は最大でも200トン、中には20トン未満などと言う物すらあった。しかし小さいと言って侮れないのは水雷艇の殆ど唯一の武装、魚雷によってもたらされる「一撃以って一艦を屠る」攻撃力であった。この「小よく大を制する」の思想と、当時の最新兵器である魚雷の組み合わせは、如何にも日本人好みの艦艇であったと言えよう。
尤も欠点も数多あった。小型なるが故の凌波性の悪さ(元々外洋で使用する事は念頭に置かれていない)であり、主武装である魚雷を放ってしまえば、再装填の為に泊地へ戻るか、水雷艇母艦に辿り着くしか無い「一発屋」と言う事もあった。しかしこの欠点も日本海軍にある限りは欠点とはならない。海岸線が必要以上に入り組んでいる我が国では、このような小型艦の泊地など探さずとも幾らでも見つかる上に、防衛戦に関する限り運用海面は勝手知ったる「沿岸」であったからだ。
これより少し前、イギリスでは各国から殺到する水雷艇の注文に応じる為に、量産の効かない艦艇用ボイラーではなく、既に工場で大量生産に移っていた性能は若干劣るが安価な機関車用ボイラーを載せた「普及版水雷艇」を提供していた。高圧ボイラーを製造した事はあるが、未だに必要量を満たす程の量産が出来ない日本はこの事例を知るや直ちにロンドンに照会をし、必要な図面と工作治具を入手したのである。勿論来たるべき日露戦に備えての事であった。
明治30年9月、海軍は逓信省を通じて各鉄道会社に対し、「目下不要ノ機關車ヲ供出サレ度」と言う要請を行う。自前でボイラーの量産が効かないなら、既に機関車として使っているボイラーを横車式に積んでしまえと言う大胆且つ乱暴な発想であった。要請には条件があり、
「一、英國若シクハ米國製ノ機關車テアル事」
これは当然の事で、治具がフィートポンド法のイギリス製である為にメトリックの諸国で製造された機関車は対象外となったのである。
「二、緊要ナル任務ニ不就事」
これが後々論議の種となった。外貨を稼ぐために生糸や銅鉱石等を牽いて走っている機関車を供出してしまっては本末転倒も良い所である。無論鉄道会社としては「緊要なる任務に就かざる」機関車など無いも同然であって、本音を言ってしまえば一両たりとも供出などしたくは無かったのである。まだ日本の鉄道は骨格線の造成途上にあって、最も古い機関車であっても車齢25年。第一線で働いていた時代であった。各鉄道会社はこの一文を盾に取り、その年の末まで唯の1両の機関車も供出はしなかったのである。
業を煮やした海軍は逓信省に対し、鉄道作業局(後の国鉄)に強制的に数両の機関車を供出するよう働きかけた。作業局は渋々これに応じたが、作業局が応じたと言う事は他の鉄道会社も座視出来ない羽目に陥ったのである。こうして明治31年5月までには全国から11両の機関車が広島に集まって来たのだ。
一応供出とは言っても海軍が永続的に使用する訳では無く、「和平ノ回復迄」と言う曖昧ではあるが期限付きの借上げで、一定の賃借料を支払う上に除籍後は現状に復して返却する、万一「戦没」した場合は相応の代車を以って償うと言う、また随分な低姿勢振りも見せた。
解体前の選考で11両の内6両が「合格」とされ、目出度く出征する羽目となった。その内の1両が冒頭の日本鉄道186号である。
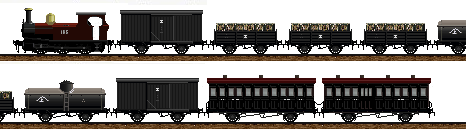
当時海軍は新造、鹵獲合わせて85隻の水雷艇を保有していたが、今は1隻でも多くの「歩」が欲しい所であった。明治31年度予算でイギリスに発注された4隻に、新規に改造される6隻の「汽車水雷」が加わればその戦力は倍加する。
明治32年から34年にかけて呉の造船所で改造されたそれら「汽車水雷」は、他の水雷艇に比べて速力で劣る所があり、6隻の内の4隻で一隊を構成(明治34年・第22艇隊、明治38年改編時・第121艇隊)、残る2隻は重要泊地の警備に回された。いずれも排水量が35~40トンであった為、「三等水雷艇」に区分されている。
日本鉄道186 1881 Sharp Stewart 水雷艇第86号 明治39年10月除籍
日本鉄道202 1891 Dubs 水雷艇第87号 明治39年10月除籍
九州鉄道16 1895 Baldwin 水雷艇第88号 明治38年12月作業中に沈没
山陽鉄道104 1898 Schenectady 水雷艇第89号 明治39年10月除籍
関西鉄道80 1897 Nasmyth Wilson 水雷艇第94号 明治38年3月航海中に沈没
作業局23 1885 Nasmyth Wilson 水雷艇第95号 明治39年10月除籍
これらの内、86、87、88、94号艇が一隊を組んで訓練をしていたが、94号艇は明治38年3月、佐世保から五島列島の監視哨へ物資を輸送する途上、福江島南東海上でノルウェー籍の貨物船と衝突して大破沈没している。その代わりに95号艇を加えて日本海海戦を迎えるのだ。

“殊勲ノ第八十六號艇”(明治43年発行の絵葉書)
日露開戦後もこれら汽車水雷は、要地から艦隊への連絡や人員・物資輸送等の余りパッとしない職務に就いていた。ロシア太平洋艦隊壊滅後に急遽組織された「第2太平洋艦隊(バルチック艦隊)」の東洋来寇が確実となると、海軍は南シナ海から対馬海峡に及ぶ広大な海面に散らばる孤島や岬等に、無数の監視哨を設けて兵を常駐させる。飛行機やレーダーが無い時代には人の目だけが頼りであった。これらの隔絶した哨所に交替人員や食料等を届ける役目は、専らこれら「員数外」の汽車水雷が当っていたのである。
海軍が音頭を取り、新聞が「汽車の出征。精鋭水雷艇となりて国難に立つ」等と宣伝されていたのだが、随分な精鋭もあったものである。
そして明治38年5月27日。敵艦見ユ。
この決戦の日に至って、汽車水雷121艇隊を含む全水雷艇隊では全員が腐り切っていた。連合艦隊からの「各水雷艇隊は三浦湾に波浪を避けよ」と言う命令が、彼らを憤然とさせていたのだ。
「目の前では大海戦が将に今行われてようとしているのに、このままでは我々の獲物がいなくなってしまう。波涛など物の数ではありません、出撃させて下さい」
各艇隊の指揮官は司令部にそう文句を付ける。しかし返答はにべも無かった。水雷総隊の鈴木指令は、そう言って詰め寄る艇隊の若い指揮官達を下がらせる一方で、この一戦は必ず勝てると思ったそうである。海戦の帰趨が定まらない前から自分達の獲り分の心配をしている。相手を呑んで掛かっている。これは高い士気あっての事だからだ。
第1次、第2次海戦の結果が徐々に判明するにつれて、艇隊員達の焦慮は募った。居ても立ってもいられない。そして遂に2300時に至って、連合艦隊司令部から命令電が入る。
「各艇隊は指定海面に急行し、残敵を掃討すべし」
喜び勇んだ水雷艇隊は、鎖を解かれた猟犬の如く、4隻1組になって激浪の日本海へ踊り出て行った。
本来出撃の予定が無かった汽車水雷86号艇でも、艇長の弥富中尉始め11名の乗組員が狂喜乱舞し、急いでボイラー圧を上げると三浦湾口から滑り出して行く。
「これまで随分と冷や飯を食わされて来たが、それも今日限りだ。ここで一番大物を頂いて指令長官の鼻をあかしてやろうではないか」
25歳と言う若さを頬髯で辛うじて隠している弥富中尉は、そう豪快に言い放って皆の士気を高めつつも、内心は不安で一杯であった。86号艇の羅針盤は微妙に北西に偏向する癖がある上、海を知悉している小寺兵曹長は負傷して入院中であった。駄目押しで主兵装である水雷発射管がここ数日故障しがちであり、と言う事は「大物」に行き会ってもこちらは艦尾の機関砲で闘うしか方法がないのだ。
海面を蒙気が覆っているのも不安材料であった。昨27日の第一次海戦以降度々海霧が沸いて見通しを阻んでいる。この霧によって僚艦を見失ったらどうすれば良いだろう、そう考え出すと胃が痛むのであった。
不安は的中する。午前7時30分頃には、既に86号艇の視界に僚艦の姿は無かった。幸い朝鮮半島の山並みは見えていたので、引き返そうと思えば引き返せる。正にその指示を出そうとした矢先、見張り員の叫び。
「艇長、黒煙が見えます」
見ると確かに2時の方角に、霧に混じってうっすらと煤煙が立ち上っているのが見える。敵艦か、味方艦か?
「よし、微速前進。見張り員、見逃すなよ」
進むに連れて次第に艦の様子が判って来る。黄色い煙突! ややあって青い十字旗! 敵艦だ! 事ここに至って、弥富中尉は腹を括った。
「各員に令達する。前方の艦は露艦である。本艇はこれより敵左舷後方より水雷にて攻撃を敢行する! 修練の一撃を見舞ってやれ! 以上」
86号艇は白波を立てないように敵艦の後方に忍び寄った。幸い敵艦は独行中のようである。艦尾に数個所破損の跡があり、もしかしたら大損害を受けているかも知れない。そうであれば反撃は少なく、或いは降伏するかも知れない。
―弥富中尉のそんな楽観は一発で吹き飛ばされた。急に海霧が晴れ、86号艇を認めた敵艦は、舷側の砲を威勢良く放って来たのだ。時に午前8時22分であった。
この敵艦は装甲海防艦「オレンブルグ」である。「ニジニ・ノヴゴロド」級の3番艦として1892年に進水した旧式艦であった。後方にきつく傾斜した2本煙突が特徴的な2本マスト艦で、舷側に4門の8インチ砲を備えていた。ロジェストヴェンスキー中将直卒のバルチック艦隊所属ではなく、本来はネボガトフ少将率いる第3太平洋艦隊に属していた。
27日の第1次海戦では、主力艦である「クニャージ・スワロフ」「オスラビヤ」等の戦艦が日本艦隊の良い的になってくれていた為破損は僅少であったが、第2次海戦で日本第2艦隊の装甲巡洋艦群が放った砲弾が右舷にくまなく命中した結果、舵機は破損し浸水が止まらなくなった。この一撃で艦長のレベデフ大佐は戦死し、28日の現時点では最先任のセロフ少佐が指揮を執っている。この時までに総員必死の応急措置で浸水は止まっていたが、6ノット以上は出せない有様であった。

リバウ軍港を出航し東洋へ急ぐ「オレンブルグ」
1905/2/19 デンマーク・スカケェラーク島にて撮影
もしも敵艦が右舷に現れたら降伏しよう、セロフ少佐はそう腹を決めていた。しかし敵艦が、未だ砲が生き残っている左舷から現れ、しかもそれがちっぽけな水雷艇であるのならば話は別だ。こいつを追い払い霧に紛れて北上すれば、巧く行けばウラジオに逃げ込めるかも知れない。―そんなセロフ少佐の楽観も、やがて吹き飛ばされる事になる。
もう弥富中尉に迷いは無かった。幸い砲撃してくるのは1門だけで、水雷艇が最も恐れる機関砲は撃って来ない。昨日の情報では露艦の砲撃精度は低く、多少距離を置けば命中する事は無いと言う事だった。
「山田!」
艇長は操舵手の名を怒鳴る。それだけで良かった。熟練した操舵手は白い歯をむき出して笑顔で応える。艇は右に左に舵を切りながら、敵艦の左舷に沿って追い抜いて行き、その間に絶好の射点を見付け出す積もりであった。
この時点でのセロフ少佐の悩みは、左舷の艦砲を斉射出来ない事であった。生き残った砲手が各備砲に取り付いてはいるが、それらが勢いに任せて一斉射撃をしでかしたら、どう控え目に見てもとんでもない事になる。右舷喫水線下の破口を塞いでいる防材が破れ、再び浸水が始まるに違いない。そうなったら戦闘どころでは無く、ウラジオへ逃げ込む夢も儚く消えてしまうのだ。
どうにかして水雷艇を追い払ってやれば良いのだが、敵の水雷艇は余程肝が座っているようで、砲弾の上げる水柱を掻い潜り、執拗に海面を蛇行しながら攻撃のチャンスを伺っている。
「機関砲はまだ使えないのか!」
「駄目であります! 給弾器が破損しております!」
午前8時40分、86号艇は敵艦の前方を猛スピードで横切り、大きく周回しながら射点を探そうとしていた。右舷側に出ると不思議な事に一発も撃って来ない。―そうか、敵め、右舷を叩かれたな。
「水雷発射準備完了!」
「ようし、撃て!」
艇首の水雷発射管から、朱式88式水雷が放たれた。放たれたが最後、86号艇には二の矢は無いのである。いや、無事に発射できただけでも86号艇の一同はホッと胸を撫で下ろしたのだ。殊にこの数日間の訓練で、1度としてまともに発射された試しが無かったのだ。
「敵水雷艇、水雷発射しました!」
「取り舵! 急げ」

「水雷、命中します!」
「南無八幡っ、当れ当れ!」
弥富中尉は最前から望遠鏡を手放さなかった。今この瞬間にも敵艦の最期が見られる、或いは我が人生の最後の瞬間かも。そう思って敵艦をじっと見詰め続けていたのである。
所が幾ら待っても水雷が爆発する様子が無い。
「艇長?」
「無念。不発であったか!」
オレンブルグの艦上では皆が右往左往していた。僅かにセロフ少佐のみが仁王立ちになり双眼鏡で雷跡を追っている。後に捕虜になったある水兵はこう証言した。
「あん時あのお堅い少佐殿の口が、こう動いてただよ。『聖母よ…』ってね」
雷跡が舷側に消えたと思った瞬間、「ゴン」と鈍い音がした。
「…不発、か? おい、あれは不発だったのか?」
生き返ったような溌剌としたセロフ少佐の声が艦上に響いた。もうこれがこの世の見納めだと覚悟を決めていた水兵達も、それに釣られて喜び勇んだ。「ウラー」を連呼する者もいる。
その時、艦底から青ざめた顔で上がって来たのは、先任下士官のミハイルである。
「少佐殿、最悪であります」
「どうした、水雷は不発ではなかったのか」
「日本人の水雷が防材を破壊しました。本艦は間もなく転覆するでありましょう」
「…何だと」
「この上は仕方が無い、一旦三浦湾に立ち戻り、他の艦隊に通報するのだ。面舵!」
「待って下さい。敵艦に白旗が揚がっています。降伏です。敵艦が降伏しました!」
「何?」
弥富中尉が再び望遠鏡を敵艦に向けると、確かに軍艦旗が下され、代りに白旗が揚がっているのが見えた。中にはシーツのような布を両手で広げて走り回っている者までいる。5月28日午前8時55分であった。
86号艇がオレンブルグの右舷に接舷すると縄梯子が降りて来た。上って行くのは弥富中尉と英語が堪能な柏木見習少尉であった。
「ロシア帝国海軍装甲海防艦オレンブルグ艦長代理、ウラジミール・ニコライェビッチ・セロフであります」
「大日本帝国海軍水雷艇第86号艇長、弥富嘉右衛門であります」
「本艦は浸水甚だしく、これ以上の航海に耐えない為、ここに貴軍に降伏します」
「本職は貴官らのご決断に敬意を表します。貴官らの勇戦を称え、俘虜として人道的に取り扱う事を確約致します」
「感謝致します。…所で、我々は降伏しましたが、既に貴官もお察しの通り、本艦は沈没しかけており、左舷が次第に競り上がって来ております。今貴官は『俘虜として人道的に扱う』と仰いましたが、一体どうやって我々を俘虜になさるお積もりか、それを伺いたい」
そう言われて弥富中尉は初めて気がついた。これまで戦闘にかまけて全く思いが至らなかったのだ。胃が再び痛み出した。
―そう言えば、どうやって露助を救出するんだ?
沈みかけているとは言え、相手は3000トン級の装甲海防艦である。生存者を数えた訳ではないが、どう見積もっても100人や200人はいるであろう。高々30トン余りの汽車水雷では、生き残った全員を救い出す事など望むべくもない。その時、86号艇から声が上がった。
「艇長! もういけません。缶がいかれました。出力が上がりません!」
職務熱心な柏木見習少尉が今の報告を逐一英訳してセロフに伝達する。
傾きかけた甲板で二人は暫し見詰め合い、引き攣った苦笑いを浮かべていた。今や敵味方共に遭難者となったのである。
仕方なく、元気な者はオレンブルグの艦内にあった浮かぶ物を海に投擲し、それらに掴まって海上を漂っている。負傷している者は86号艇に引き揚げ、代わって日本水兵が水に入り、艇の舷側に掴まって立ち泳ぎをしていた。既に重みで86号艇自体が沈みそうであった。
水平線上に一条の煤煙が見られたのはそんな時であった。午前11時頃である。一時は敵艦か、と騒然となったが、やって来たのは砲声を聞いて飛んで来た日本海軍の通報艦「壱岐」であった。その姿を目にして最も喜んだのが、弥富中尉であったか、セロフ少佐であったかは今となっては判らない。
これが86号艇の戦争であった。
86号艇はその後、壱岐に曳航されて佐世保に戻り、補修を受けて瀬戸内海の警備に当った。当時の新聞は日本海海戦の大戦果で持ちきりとなっていたが、その熱もやや冷めた明治38年7月、東京読捨新聞に「汽車水雷艇大戦勝! 排水量百倍の敵艦を降す」と言う見出しが踊った。その記事には敵艦降伏後に86号艇も故障し、敵味方があわや漂流者となりかけた事など微塵も載っておらず、唯、「代用品に過ぎなかった汽車水雷艇が敵艦に痛打を与え、遂に此れを降伏の已む無しに至らしめた」とだけ書いてあった。
それで充分であった。少しでも海軍の戦力を増す為に全国から集められた機関車達の名誉を称えるには、もうそれだけで充分であった。
86号艇は少ない汽車水雷の中でも、唯一敵とまみえ(例え不発魚雷の戦果であっても)これを降したと言う戦果を上げた「強運の持ち主」であると言われた。86号艇、いや日本鉄道186号を戦地に送り出した小山機関庫の一同も、我が事のように喜んだ事は言うまでも無い。
所で、海軍は各鉄道会社から機関車を借り受けるに当って「和平の翻復まで」と言う期限を打ち出したが、ポーツマス条約が成立して日露戦争が事実上終結しても尚、彼ら汽車水雷は故郷に凱旋出来なかった。応召した6両の機関車の内、生き残った4両は既に水雷艇のボイラーとしての役目を終え、宇品駅で保管されていた元の車体と涙の再会を果たしたのであるが、その立場は尚も「出征中」のままであった。これには理由がある。
日露戦争の終結後、国は主要鉄道会社の買収を計画していた。本来であればロシアから取れる筈の賠償金を以って買収費用に弁ずる予定であったのだが、ご存知の通り、ポーツマス条約は賠償金の取れない条約である。そこで外債を起こしてこれらの費用に宛てる事になるのだが、この時期ロンドンの金融市場はオーバーローンで起債が出来ない状態であった。じきにパリ市場が開放されて資金に困る事は無くなるのであるが、その間私鉄の買収は遅々として進まなかった。これらの機関車は元の使用者に返されて然るべきなのだが、こうした事情があって、未だに海軍貸し出し中のままになっていたのである。
ようやく明治40年の声を聞くと、彼ら4両の機関車は満艦飾の状態でそれぞれの故郷へ凱旋して行った。
元日本鉄道186号機は故郷の小山に戻って「112」と名称を改め、大正の終わり頃まで両毛線や水戸線で混合列車を牽引していた。

昭和初年、112は高崎に移り入換用として構内を右往左往した後、昭和24年に老朽の為廃車される運びとなった。機関車不足の折から私鉄への売却話も出たが、足回りの老朽化はいかんともし難く、廃車が決定されたのである。
さて、この話はここで終わりではない。日鉄186→水雷艇86号→112のボイラーが持つ強運はこんな所で終わる物ではないのだ。
信越線の横川~軽井沢間は既に明治44年から電化されていたが、それ以来同地で使用されていた小型暖房車(ヌ100等)が老朽化して使い物にならなくなっていた。同線の特殊な事情により車体長の短い暖房車が必要とされた為、白羽の矢が立ったのが、廃車が決定して現在休車中である「112」のボイラーであった。
車体は解体されたが、明治31年のあの日と同じくボイラーは丁重に外され、戦時無蓋車のトキ900の足周りに載せられ、儀装された。こうして日鉄186のボイラーはその主を二転三転させながらしぶとく生き残り、今度は「ホヌ4901」として奉公する事となったのである。
速度制限の厳しいトキ900の足でも、碓氷線でならば問題にならない。そもそもの速度が20キロを超える事など無いからだ。こうしてホヌ4901の碓氷峠での活躍は昭和38年まで続いた。
昭和38年から40年までの間を再び高崎で過ごし、その後水戸機関区へ移ったホヌ4901は、僚車4902と共に主に水郡線で運用に就いた。朝夕に水戸から常陸大田まで走る通勤列車はそれまで水戸の8620が牽引していたが、40年の改正でDD18に交替する事が決まり、暖房用蒸気発生装置を持たない同機と手を組んで昭和46年まで走り続けた。

赤いディーゼル機関車の後ろをのんびりゆったり煙を吐いて附いて行く暖房車。その煙は、かつて利根川流域に文明の光をもたらした煙であり、海霧に覆われた日本海で敵艦と命のやり取りをした煙であり、そして再び故郷の山野で平和に立ち上る煙なのだ。